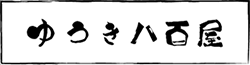1989年からはじまった“バランゴンバナナ”の民衆交易。持続可能なバナナの栽培が地域の自然を守り、フィリピンの生産者たちの暮らしを支えることにもつながっています。ほんのりとした酸味とコクのある味わい!
バランゴンバナナについて
バランゴンバナナ(Balangon Banana)は、フィリピンで10種類程度あるバナナの品種のうちのひとつです。
バランゴンバナナが初めて日本に届けられたのは1989年。1980年代に起きた砂糖の国際価格の暴落で、サトウキビのプランテーションが広がるネグロス島では、仕事を失った多くの労働者とその家族が深刻な飢餓に見舞われました。1987年にフィリピン・ネグロス島の人々の自立を支援する取り組みの一環として、マスコバド糖の輸入が開始されたのが「民衆交易」の始まりです。そのマスコバド糖に続く第2の商品として考えられたのが、このバランゴンバナナでした。
数ある品種の中からバランゴンバナナが選ばれたのは、そのほんのりとした酸味と甘みが調和したコクのある味わいが、日本人好みだったことがあります。また、主に山間地で自生、栽培されていて現地であまり流通していないので、日本へ輸出しても現地で暮らす人たちの食を奪うことにならない、ということも考慮されました。
バランゴンバナナの民衆交易により、生産者は安定した収入が得られるようになり、子どもの教育費や基本的な衣食住を確保する一助となっています。バランゴンバナナを味わうことは、フィリピンの生産者たちの暮らしを応援し、持続可能な社会づくりへとつながっています。
ネグロス島から始まったバランゴンバナナの交易は、今ではルソン島、ボホール島、ミンダナオ島にも広がり、合計4つの島から届いています。
見た目が良くないバナナでも

少しキズがあったり見た目があまり良くないバランゴンバナナでも、厚めの皮が中の実を守ってくれています!葉のこすれや輸送中にできた傷があっても、皮をむいたらほとんど中身には影響がありません。また、収穫の時についてしまったバナナの樹液が酸化して黒くなったり、砂ぼこりがついて白くなってしまったような跡がみられることがあります。乾季から雨季への移行期などに皮が赤くアザのようになってしまうこともありますが、食味や安全には問題がありません。

栽培期間中、化学合成農薬や化学肥料は使用していませんが、植物検疫の結果、青酸ガスや燻蒸を受けることがあります。青酸ガスは揮発性が高く、果実の中に残留しにくく安全性が高いものです。
保管方法
バランゴンバナナの産地は、現在ネグロス島をはじめとする4つの島から届いています。そのため標高や栽培条件が一定ではなく、熟度にバラつきがでます。また、配送中の傷みを防ぐために、青めでのお届けとなる場合があります。防カビ材や防腐剤を使用していないため、特に軸の部分に白いカビが生えたり傷みやすいです。届いたら袋から出して風通しの良いところにおいてください。
◎青いバナナが届いたら
15℃以上の場所に保管。口を開けたポリ袋や紙袋に入れてください。熟したバナナやりんご、キウイと一緒に保管すると早く追熟します。まれに青いまま熟している場合があり、実が柔らかければ食べられることがあります。(バランゴンバナナは、現地では緑のまま熟します)
◎熟したバナナが届いたら
風通しのよいところで保管してください。冷蔵庫に保管もOK(皮は黒くなりますが、中の実は食べられます)。その場合、新聞紙などに包んでください。皮をむきラップで包み、冷凍もおすすめです。
※ゆうき八百屋では、フィリピン産バランゴンバナナの他、メキシコ産、エクアドル産、ペルー産のオーガニックバナナなども取り扱っています。